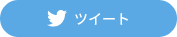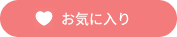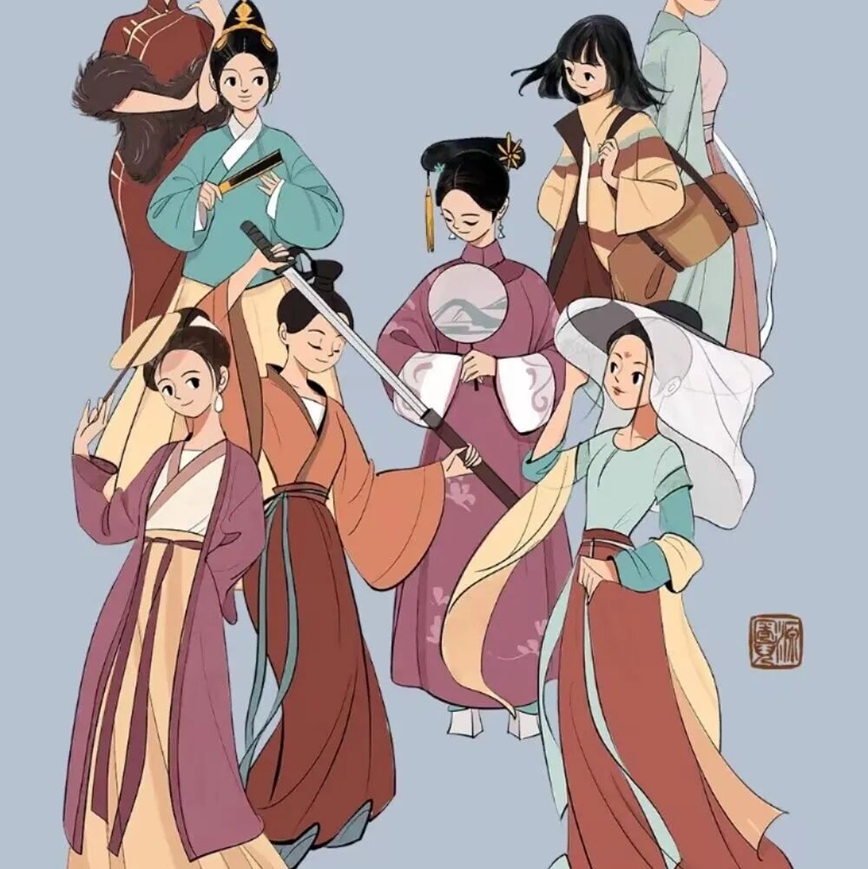青花磁器は「青く」ない?
もし「中国を代表する磁器を一つ選べ」と言われたなら、多くの人が青花磁器(染付)と答えることだろう。青花磁器を見たことがない人は、その名前から華やかで目の醒めるような青を想像してしまうかもしれないが、実際には「青」というより深い「藍色」、それも特別な藍色をしている。
そんな青花磁器の登場はまさに彗星のようだ。それまで中国磁器は青磁と白磁を双璧として一歩一歩発展してきた。しかし元代に入って青花磁器が現れると、瞬く間に中国磁器の主流となり、中国のみならず世界中を風靡してしまった。まさに「生まれながらの王者」としか言いようがない。

イスラム文化の影響を受けていた元朝人にとって、藍色はとても崇高な色だった。彼らはその藍色を磁器上で表現するため、コバルトを釉薬として用いることを思いついた。青花磁器は白磁の素地に模様を描き、その上に無色透明の釉薬をかけて1200度以上の高温で一度に焼き上げることで作られる。青花磁器に使われるコバルト釉の種類は様々だが、そのうちペルシアの蘇麻離青(スマリチン)が最上とされる。明代の鄭和の西洋巡航によってもたらされたというこの貴重な顔料を使って焼き上げられた青花磁器は、素地に入り込んでまるでラピスラズリのような潤いと深みを帯びた色彩を放ち、所々にできる自然な滲みや斑点があたかも水墨画のような幻想的な景色を作り出す。

蘇麻離青の他にも、例えば康熙期に国産のコバルト釉を用いて生み出された「翠毛藍(すいもうらん)」は、その名の通りカワセミ(翠鳥)の羽毛のように幾重にも重なって濃淡や粗密を織りなし、その深い艶と豊かな色合いは、当時の全世界の注目を再び青花磁器に集めさせた。

著名陶磁器収集家の馬未都は「『青花』磁器とはなんとも詩的な名前ではないか。古代中国の陶磁器の中でも、こんなにロマンに満ちた陶磁器は他にない」と評価する。青花磁器はこうしたロマンによって中国文化の必然として誕生し、色褪せない魅力を今なお放ち続けている。
青花磁器は「俗っぽい」?
誕生から700年あまり、はじめは皇帝御用の品としてのみ作られていた青花磁器は、皇帝たちの美意識やそれぞれの時代性を反映しながら次第に民間の日用品として使われるほど中国社会に浸透していった。現在我々が日常的に触れる青花磁器は決まった文様ばかりで、人によってはひどく形式的で俗っぽく感じることだろう。しかし、青花磁器の世界に一歩踏み入ってみれば、こんなに多様で特色的なのかと驚くはずだ。
例えば過去のオークションで3300万米ドルの高額で売買された『鬼谷子下山大罐』などはその力強さ、奔放さに一目で惹き込まれる。度量の大きさを感じさせる器形に乱世の策略家・鬼谷子の故事が持つ気勢も加わって、山が唸り、虎が吠え立つような、草原民族である元朝人の豪胆さが伝わってくる。

また宣徳期の『一束蓮紋盤』は、あたかも青い蓮の花が盤の中で屹立しているかのような印象を与える逸品だ。のびやかに広がる茎と様々な角度で描かれた蓮の花の秀逸な造形、そしてもやがかった水辺を彷彿させる淡い滲みからは、水墨画のような美しさと最盛期の明朝の気勢がうかがえる。

同じ明朝でも、国力が衰退してきた成化期のものになると顕著におとなしい雰囲気になる。例えば『青花纏枝紋宮碗』一揃えのアオイの花やツタの文様表現は、先ほどの宣徳期のものに比べ随分簡素だ。しかしそれが却って一気呵成に描かれた線の流麗さを引き立て、淡々とした余白も逆に清雅な静けさを感じさせる魅力となっている。

清・康熙期の作品も大胆な余白が特徴だが、山水画や題字が施され、さらに文人好みの作風となる。例えば『康熙青花月影玉蘭図観音瓶』の胴には、遠くにかすむ山々と近くの草花のコントラストが美しく描かれ、思わず磁器ではなく一幅の山水画を鑑賞しているような気持ちにさせる。

青花磁器を鑑賞するとまずこの世の全てが描かれているような満載さが目に飛び込んでくる。しかし静かに、そして真摯に向き合ってみてほしい。次第にその純粋さや静けさが見えはじめ、青花磁器の雅と俗が感じられるようになるはずだ。
青花磁器は「オワコン」?
清代中後期頃になると青花磁器の製作技術はますます円熟する。しかしその美的表現は逆にどんどん陳腐になってゆく。青花磁器の凡庸化は止められないのかと思っていたころ、「中国青花雪景の第一人者」と呼ばれる陳麗女史の作品に出会った。冬の黄山の雪景色を花器に描いたその作品は、幾層にも塗り重ねた釉薬の上に絵画のような隈取りと線描を施し、さらに古器風の風合いを再現することで、フカフカした雪の質感と幽雅な世界を見事に表現している。

また李雅雯女史の茶器「青花」シリーズでは、揉みちぎられた水墨画のような非常に淡い表現を見ることができる。細かな描画を施さず、濃淡の異なる釉薬を施したあとに彫ったり削ったりすることで浮かび上がる素朴な地肌の質感を巧みに利用し、伝統に縛られない清雅な世界観を表現している。

こうした現代の作家の手によれば、青花磁器は山水画の世界のような古式然とした姿にも、逆に水煙のように淡く風雅な姿にもなる。思い出してほしい。青花磁器は我々中国人の意識と魂に常に刻まれ続けてきた。そして彼らはいつでも、より優しく美しい姿へ孵化する機会をうかがっているのだ。
移ろう時間の中で青花磁器は何度もそのかけがえのない美しさを我々に見せてくれる。それこそが青花磁器の底力だ。美しいものは優しい人に似ている。探してもなかなか出会えるものではないが、いつの時代にも必ず存在する。そして偶然彼らに出会えた時、すれ違うことなく、寄添ってその姿を静かに眺めることができれば、それは何より至福なひと時だろう。
「歩いて旅を見る」より